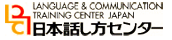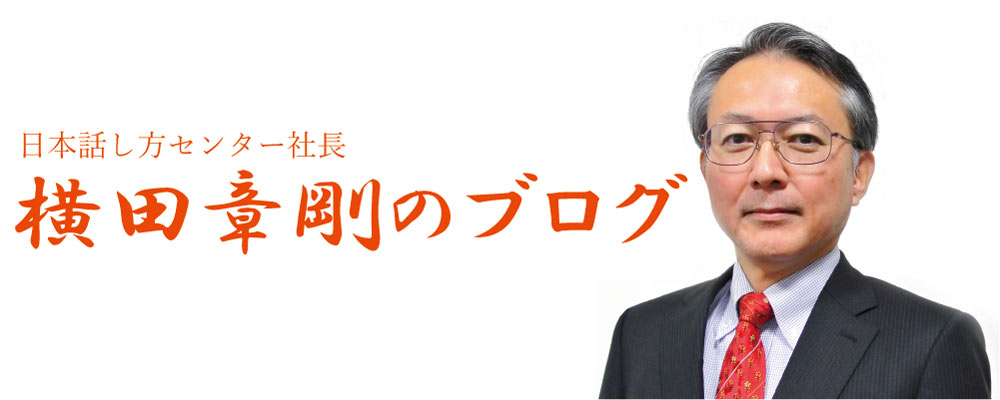2019年12月14日「動詞表現」ではなく「動作表現」を使う
浅田すぐるさんというコンサルタントの著書に「すべての知識を『20字』でまとめる」という本があります。
とても参考になることが書かれている本で、私は折りに触れ読み直しています。
今回はこの本に書かれていることで、特に私が「なるほど!」と思ったことをご紹介します。
それは、行動に移したいなら「動詞表現」を「動作表現」にする、ということです。

私たちは、日頃から人や組織に動いてもらうために、話をしたり、文章を書いたりしています。
しかし、思い通りに人や組織が動かない、ということは実に良くあることです。
思い通りに動いてくれることがほとんどない、といってもよいかも知れません。
浅田さんは、その原因の一つに、我々が一般的に「動詞表現」を多用しているからではないか、と考えています。
「動詞表現」とは、例えば、
・目的を意識しよう
・組織に浸透させよう
というものです。
一般的によく使う表現です。
しかし、この表現では、何をしたらいいのか、具体的な行動がわかりません。
これに対して、「動作表現」というのは、
・意識したい目的が書かれた紙を朝出勤したら必ず見よう
・組織に浸透させたいメッセージを毎日全員で唱和しよう
というものです。
浅田さんは、このような「行動に移せるレベルの表現」を用いるべきだと説いています。
確かに、人間の行動とは極めて具体的なものです。
単に「曲がれ!」と言われても戸惑いますよね。
「次の交差点の手前を左に曲がれ!」
などと具体的に言われないと、道を曲がることもできません。
しかし、私たちはビジネスにおいて、この「曲がれ!」レベルの話をしていることが多いのではないでしょうか。
それは、「曲がれ!」と言えば、どこでどのように曲がるのかは、言われた人が判断するだろう、と考えているからだと思います。
しかし、人は抽象的な話を聞いて、それを具体的に行動レベルまで咀嚼できることはまれです。
だから、いくら言っても、他の人や組織が曲がってくれない。
言った人は「何故曲がらないんだろう・・・」と思っている。
例え話で恐縮ですが、このようなことが職場で日々繰り広げられているのではないか、とこの本を読んで、改めて思いました。
そして、もう一つ気付いたことがあります。
それは、日本話し方センターの話し方教室では、この「動作表現」で受講生の方々に行っているアドバイスが多いということです。
「家でスピーチ練習をしてください。」ではなく、
「家で声に出して、30回以上、時間を計ってスピーチ練習をしてください。」
とお願いしています。
また、
「もう少し高い声で話した方が、声の通りがよくなりますよ。」ではなく、
「地声が『ド』の音だとすると、『ソ』か『ラ』の音で話してください。」
とアドバイスしています。
こうしたことも、60年以上続いている私たちの教室の強みなのではないか、と改めて思いました。